



 ホームページに戻る
ホームページに戻る
: 2 胸が苦しい
: 循環器疾患
: 目次
目次
索引
1 ショック状態
![\begin{table}[H]
\scriptsize\leftmargini=1zw
\STRUCT{ショックの鑑別}{}{
\ACTION{...
...00mgの静注を考慮}}
\ENDIF}
\ENDIF
}%
\normalsize\leftmargini=2zw
\par\end{table}](img2.png)
- まずは血圧を維持し、その間にショックの原因検索を行う。
- 血液ガス検査と心エコーだけで、ショックの原因は結構わかる。
- ショック状態の続いている患者を、病棟から出してはいけない。検査はなるべくポータブルで。

|
|
輸液路を確保する
生食/ラクテックを500ml全開で開始
1。
|
- 1 心不全がある患者であっても、ショック状態なら治療は同じである。
|
|

|
カテコラミンを使う
- イノバン3A+生食85ml を5ml/hより開始
- ノルアド1A+生食20ml を0.5mlずつ静注
|
|

|
血液ガスをとる
- アシドーシスがある
 非常に危険な状態 非常に危険な状態
- 低酸素がある
 酸素投与 酸素投与
|
|


|
胸部単純写真をとる
- 縦隔の偏移
 緊張性気胸 緊張性気胸
- 肺うっ血
 心原性ショック 心原性ショック
|
|

|
胃洗浄を考慮
- 凝血が引ける
 上部消化管出血 上部消化管出血
|
|

|
動脈ラインをとる
- 治療抵抗性のショックの場合
- 血液ガスを経時的に測定したい場合
|
|
1.1.1  単位について
単位について
昇圧薬の量は、
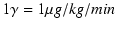 で計算される、
で計算される、 という単位を用いる。"
という単位を用いる。"
 さんにはイノバン7
さんにはイノバン7 、ノルアド0.07
、ノルアド0.07 が入っていますが、まだ血圧が上がりません"などというように使われている。
が入っていますが、まだ血圧が上がりません"などというように使われている。
しかし、オーダー票には で指示が出されることはない1。
で指示が出されることはない1。
 単位は医者同士のコミュニケーション手段としては大切なので、
自分の受け持ちにカテコラミンが大体何
単位は医者同士のコミュニケーション手段としては大切なので、
自分の受け持ちにカテコラミンが大体何 程度用いられているのか、
主治医は常に把握しておく必要がある。
程度用いられているのか、
主治医は常に把握しておく必要がある。
昇圧薬としては、以下の3つがよく用いられる。
1.2.1 心タンポナーデ
- 心膜炎、心筋梗塞に合併し得る。
- 心のう水の貯留とタンポナーデの状態は違う。少量の貯留であっても急速に貯留してくる場合は容易にタンポナーデになり得る。
- タンポナーデの診断は以下のとおり。
- 奇脈を生じている。
- 血圧低下、頸静脈の怒張、肝腫大
- 心エコー上患者の吸気時に下大静脈が拡張
1.2.1.1 奇脈の測定
- 患者橈骨動脈の脈を触れ、患者の吸気で脈の消失を見る
- 患者の呼気時に収縮期血圧を測る
- そのまま息を吸ってもらい、さらに血圧を測定して吸気時の収縮期圧をはかる
- 両者の差が10mmHg以上あれば奇脈である
症状のある患者で心のう水の貯留を見たら、とりあえず穿刺する。
- タンポナーデであれば、わずかなドレナージでも劇的に症状が回復する。
- 実際、心のう内圧の実測以外のタンポナーデの診断はしばしば当てにならないという。
- P.
![[*]](crossref.png) 参照。
参照。
- 塞栓が巨大な場合にショックを生じることがある。
- PCPSを挿入できれば必ず救命できるので、ショックを合併した肺塞栓患者においてはこうした道具の使用をためらってはならない。
1.2.3 アナフィラキシーショック
- 重篤なアナフィラキシーは救急外来では少ない。
- 外来での頻度は、全ての入院患者のうち0.02%と報告されている。
- 一方造影検査を行う施設や手術室などでは、この疾患の頻度は非常に高い。
- 特に
 遮断薬内服中の患者はアナフィラキシーのハイリスク群になる。
遮断薬内服中の患者はアナフィラキシーのハイリスク群になる。
- 血圧の低下以外に皮疹、喉頭浮腫、喘鳴、嘔吐や下痢を生じる。
- 約6%の患者は、初期の発作から12-24時間後に遅発性の発作を再発する。
血圧の低下に対する対処が全て。
- すぐにラクテック/生食でラインをとり、全開で開始。
- ボスミンを0.3-0.5ml筋注する3。症状が緩解するまで5分ごとに。
- その他サクシゾン200-500mg4の静注、ポララミン5mgまたはアタP25-50mg の静注、H2遮断薬5の静注を考慮。
- P.
![[*]](crossref.png) 参照
参照
- MI患者の突然の血圧低下は心タンポナーデ、心室中隔穿孔の可能性がある。
- P.
![[*]](crossref.png) 参照
参照
- 教科書的には胸Xpを待たずに前胸部第2-3肋間を穿刺/脱気するよう勧めている。
- P.
![[*]](crossref.png) 参照
参照
- 便潜血は急性発症したような消化管出血でもたいてい陽性になり、当てになる。
- P.
![[*]](crossref.png) 参照
参照
- 一般の昇圧薬、輸液、抗生物質以外に以下のようなものがトライアルされている。
- 1日200mg程度のハイドロコーチゾン静注
- バソプレシン1単位/h程度の持続静注
- 活性化プロテインCの静注




 ホームページに戻る
ホームページに戻る
: 2 胸が苦しい
: 循環器疾患
: 目次
目次
索引
admin
平成16年8月5日
![\begin{table}[H]
\scriptsize\leftmargini=1zw
\STRUCT{ショックの鑑別}{}{
\ACTION{...
...00mgの静注を考慮}}
\ENDIF}
\ENDIF
}%
\normalsize\leftmargini=2zw
\par\end{table}](img2.png)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() で指示が出されることはない1。
で指示が出されることはない1。
![]() 単位は医者同士のコミュニケーション手段としては大切なので、
自分の受け持ちにカテコラミンが大体何
単位は医者同士のコミュニケーション手段としては大切なので、
自分の受け持ちにカテコラミンが大体何![]() 程度用いられているのか、
主治医は常に把握しておく必要がある。
程度用いられているのか、
主治医は常に把握しておく必要がある。